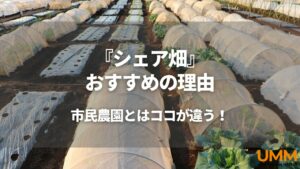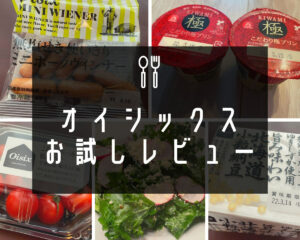ネギの栽培方法|プランターでの育て方や害虫・病気対策もあわせて解説!

※当記事はアフィリエイト広告を含みます。
ネギは料理の用途も多く、とても便利な野菜です。
また、栽培もしやすいため、初めての野菜栽培にも向いているでしょう。薬味用に使う葉ネギであれば早めに収穫することも可能です。
最近話題の「リボーンベジタブル」と呼ばれる野菜の再利用にもピッタリです。根本を残しておいて水や土に植え直すだけで新しいネギを育てる方法が人気ですね。
今回の記事では、「ネギの栽培を始めてみたい」「ネギの栽培がうまくいかない」という人に向けています。
ネギの栽培方法だけではなく、栽培のポイントも合わせて解説していきます。
1からネギの栽培を始めたい人も、初めての人も一緒に確認しながら進めていきましょう。
目次
ネギは育てやすい野菜

最初はネギについて簡単に解説していきます。
ネギは年間を通して栽培しやすい野菜なので、「野菜の栽培は初めて」という人にも向いています。
ネギの栽培時期は1年中可能
ネギの生育適温は20°c前後ですが、適温ではなくても生育します。
非常に強い部類の野菜なので、初心者でも失敗が少なく栽培から収穫まで行えるでしょう。
長ネギの場合には種を春にまき、冬に収穫することが多く、葉ネギの場合は春から夏に種をまき、収穫時期は夏から冬までが多くなります。
どのような環境下でも育てられるネギは野菜栽培初心者にぴったりの野菜です。
ネギは大きく分けて2種類
ネギの品種は多いですが、一般的に知られているのは大きく分けて「根深ネギ」と「葉ネギ」の2種類でしょう。
根深ネギは白ネギや長ネギと呼ばれることもありますが、主に根の白い部分を食します。
葉ネギは青ネギや万能ネギとも呼ばれ、緑の部分を薬味で使うことが多くなります。
根深ネギの栽培は白い部分の根を育てていかなくてはいけないため、栽培の工程が多くなることから初心者向けではありません。
反対に葉ネギの栽培は比較的簡単で、家庭菜園でも十分に可能な初心者にもおすすめの野菜栽培ですよ。
ネギを栽培するための事前準備

続いてはネギを栽培するための事前準備を確認していきます。
土づくりが基本となりますが、鉢植えやプランターといった家庭菜園向けにも準備していきましょう。
ネギに適した土を用意する
葉ネギ、根深ネギともに排水性と保水性のバランスが良い弱酸性から中性ぐらいの土が適しています。
ph6.5〜7.0が適正値になるため、石灰で調整をしましょう。
種まきや定植をする2週間ほど前に石灰を混ぜ込み、1週間ほど前に堆肥や肥料を加えて耕していきます。
石灰で基本となる土壌を作り、堆肥と肥料で整えると考えてください。
土を中和させるのに必要な苦土石灰について、別の記事で詳しく紹介しています。是非参考にしてみてください。
鉢植えやプランターの場合
葉ネギの場合には鉢植えやプランターでの栽培も可能です。深さは20cmほどのものを用意しましょう。
土は市販されている野菜用の培養土を使えば簡単です。自分で1から土作りをする場合には腐葉土や石灰、肥料などを混ぜることになります。
特にこだわりがない場合には市販の土を使いましょう。
深ネギもプランターで栽培することは可能ですが、葉ネギと比べて難しくなってしまうため、畑での栽培をおすすめします。
さらに、家庭菜園初心者向けのプランター野菜について知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
ネギの栽培方法

ここからはネギの栽培方法を解説していきます。
根深ネギと葉ネギでは違う部分もあるため、しっかりと確認していきましょう。
種まき(播種)
種まきは直まきとセルトレーを使って育苗する方法の2通りになります。
栽培する量が多い場合の直まきでは播種機を使ったほうが効率は良いですが、手でも問題はありません。
種の間隔は5mmほどで深さは1cmほどにしましょう。
手で種をまく場合は人差し指で軽く土を押し込み、種をまいて覆土していきます。
支柱などを使って一直線に窪みをつけてタネをまいても大丈夫ですよ。
直まきではなく、セルトレーを使って育苗する場合は乾燥に注意が必要です。
セルトレーの穴はひとつひとつが小さく、土は少ないため、乾燥に注意し、水と同時に液体肥料を混ぜて定期的に与えるようにしましょう。
気温が低い時期であれば不織布やハウスの日除けなどを発芽までかぶせて保温しておきます。
根深ネギは植える時に深さがある独特の形の畝が必要になるので直まきは向いていません。
セルトレーなどを使った育苗と定植が基本になります。
定植
セルトレーなどで苗を育てた場合には、一定の大きさになれば定植していきます。
ネギを軽く引っ張って、根がトレーの土を囲んでいれば定植しても大丈夫です。
すでに間引くサイズになっているので、定植する際の間隔は葉ネギであれば3cmほど、根深ネギは5cmほどの間隔で植えていきましょう。
葉ネギは指で土を軽く押して根まで埋まる深さにして、トレーの土ごと植えていきます。
根深ネギは深さが必要なので、畝に深さと幅が15cmほどの溝を作ります。
溝の片面を支えにするように植え、ワラや乾燥させた草を敷いて乾燥対策をしていきましょう。
間引き
ネギの丈が5cmほどになれば1回目の間引きを行いますが、最初は多く間引かずに2本の間1本を間引くようにします。
葉ネギは丈が10cmほどになれば2回目の間引きで間を3cmほどに間引いていきましょう。
最初から間隔が開いている箇所は間引かなくて大丈夫です。
根深ネギは葉ネギと比べて太く成長するので、株と株の間は5cm以上あけるようにします。
ただし、ネギは隣同士の根がお互いに張ることで倒伏を防げるため、間隔のあけすぎには注意しましょう。
追肥と土寄せ
葉ネギの追肥は月に1回ほどの間隔で行います。
1平方メートルあたりに対して、化成肥料一握りを目安に追肥していきましょう。
根深ネギは追肥と土寄せを同時に行います。
合計で4回の土寄せと3回の追肥を行うため、1回の土寄せの量が多くなりすぎないようにします。
定植後から50日ほどで1回目の土寄せと追肥を行い、残り2回は3週間ほどの間隔で行いましょう。
最後は土寄せのみで追肥は必要ありません。
野菜作りに重要な追肥と元肥については、こちらの記事で詳しく紹介しています。是非参考にしてみてください。
収穫
葉ネギの収穫は種をまいてから60日ほどが平均となります。
タイミングが難しく感じる場合には丈が50cmぐらいで収穫しましょう。
収穫時は根本をしっかりと握って真上に引くとすんなりと抜けます。
上の方を持って引くと、ちぎれてしまうことが多くなるので注意が必要です。
根深ネギの収穫は青い部分の成長が止まってから40日後ぐらいを目安にしましょう。
収穫する時は葉ネギとは違いそのまま引き抜かずに、側面の土をクワで掘り下げてから斜めに引き抜きます。
根深ネギの収穫時期は難しく感じるかもしれませんが、最後の土寄せから3〜40日後ぐらいを1つの目安にしてみてください。
ネギ栽培のポイント

ネギの栽培は初心者でも簡単に始められますが、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
いくつかに分けて解説していきます。
日当たりと風通しが重要
ネギは日当たりと風通しの良い場所のほうが生育は良くなります。
ただし、日当たりが悪い場所でも生育はします。
あくまで、「良いほうが好ましい」というぐらいなので、大きく気にする必要はありません。
日当たりと風通しが良ければ、より成長させやすくなるでしょう。
水はたっぷりと
他の野菜にも言えることですが、発芽までは土が乾かないようにしましょう。
発芽してからは、鉢植えやプランターの場合には土が乾いている時に水をたっぷり与えます。
水やりの時間帯は朝か夕方が基本になります。
夏など、日中が高温になる時期では、昼間に水を与えると水が高温になり、水蒸気となって根を傷めてしまうので注意しましょう。
また、露地栽培の場合、多くの水やりは必要ありません。
基本的には雨に任せておいて、1週間ほど雨が降らない場合には水を与えましょう。
露地は地中に多くの水を含んでいることが多く、地表が乾いていても根が地中から水を吸い上げるので、やりすぎには注意が必要です。
水はけの良い土を使う
ネギは強くて栽培しやすい野菜ですが、湿度には弱い性質があります。
水はけが悪く、水がたまりやすい場所だと、根腐れなどが起きやすくなるので注意しましょう。
鉢植えやプランターの場合には土自体が少なく、底から一定の水は抜けていくので問題はありません。
しかし、土が乾いていない状態で水を与え続けるとプランターでも根腐れを起こしてしまいます。
露地栽培の場合は水はけの悪い土地だと人の手では調整ができないので、あらかじめ確認しておきましょう。
リボーンベジタブルの方法

リボベジと略して呼ばれることの多いリボーンベジタブルはネギにぴったりの方法です。
長ネギでも可能ですが、葉ネギの場合は成長も早く簡単です。
根から10cmほどを残して使う部分を切り落としましょう。
あとは少し深めの瓶などに水を溜めて根の部分を浸しておくと、どんどんと伸びてくるので、使いたい部分を切り落として再度、利用できます。
根本がヌメっとしてきたら洗い流せば問題なく成長しますよ。
味や香りは落ちてしまいますが、成長を楽しめる方法になるでしょう。
リボベジは一番、簡単に始められる野菜栽培かもしれませんね。
スーパーなどで買ったネギを使って、本格的な野菜栽培の前にリボベジを試してみてください。
ネギの栽培で注意する病害虫

ネギはその年によって病害虫の発生率が変わってきます。
気候などによって流行する病気や害虫が違い、年によっては収穫に大きく影響します。
薬剤散布だけではなく、周りの農家さんの情報を聞くのも良い方法ですよ。
病気
ネギの病気は「さび病」と「べと病」の発生があります。
さび病は24°を超える高温時期には発生しにくい病気ですが、ネギの育成初期や収穫時期に現れる可能性があるでしょう。
伝染する病気なので、発生を発見した場合には速やかに抜き取るようにして、周りのネギへの拡散を予防します。
基本的には発生する前の薬剤散布による予防が好ましいですが、発見した場合にも抑制するために薬剤の散布を行います。
べと病は気温と湿度が高い時期に発生しやすいカビの一種で、丸い病斑が特徴で見分けやすいでしょう。
ネギの密度が高くなりすぎないように間引きをしっかりと行うことで多少は予防ができます。
発生してしまった後の回復は難しいため、最初の発病を見逃さないように農薬の予防散布を心がけましょう。
害虫
害虫では「アザミウマ」や「ハモグリバエ」、「ハスモンヨトウ」の発生が中心になります。
ネギにつきやすい害虫はいずれも葉の中に入り込むため、発生してしまうと薬剤が届きにくくなります。
一番の予防は早期に発見することと定期的な薬剤散布になるでしょう。
どの害虫も葉に虫が食べた跡の点や線が入るため、比較的、簡単に発見できます。
コンパニオンプランツで病気・害虫対策
無農薬野菜を栽培するときに、病気や害虫被害を抑えるために、他の野菜と組み合わせて育てる方法をコンパニオンプランツといいます。ネギ、ニンニクなどのネギ類は、独特な香りを持つことからコンパニオンプランツで病気・害虫対策としてよく用いられます。
よく相性が良いと言われている野菜は、トマト、ナス、キュウリ、ズッキーニ、イチゴなどが挙げられます。その他にもたくさんありますので、コンパニオンプランツについての記事を参考にしてみてください。
まとめ
ネギの栽培は初心者でも始めやすい野菜です。
基本的には、どのような環境下でも育つ野菜ですが、水切れや病害虫には注意しましょう。
葉ネギはプランターなどでも簡単に栽培できますが、根深ネギは少し難しくなります。
根深ネギは畝の作り方や土寄せも独特なので初心者であれば葉ネギの栽培から始めるのが良いでしょう。
みなさんも今回、解説した栽培方法やポイントを参考にネギの栽培を初めてみませんか?