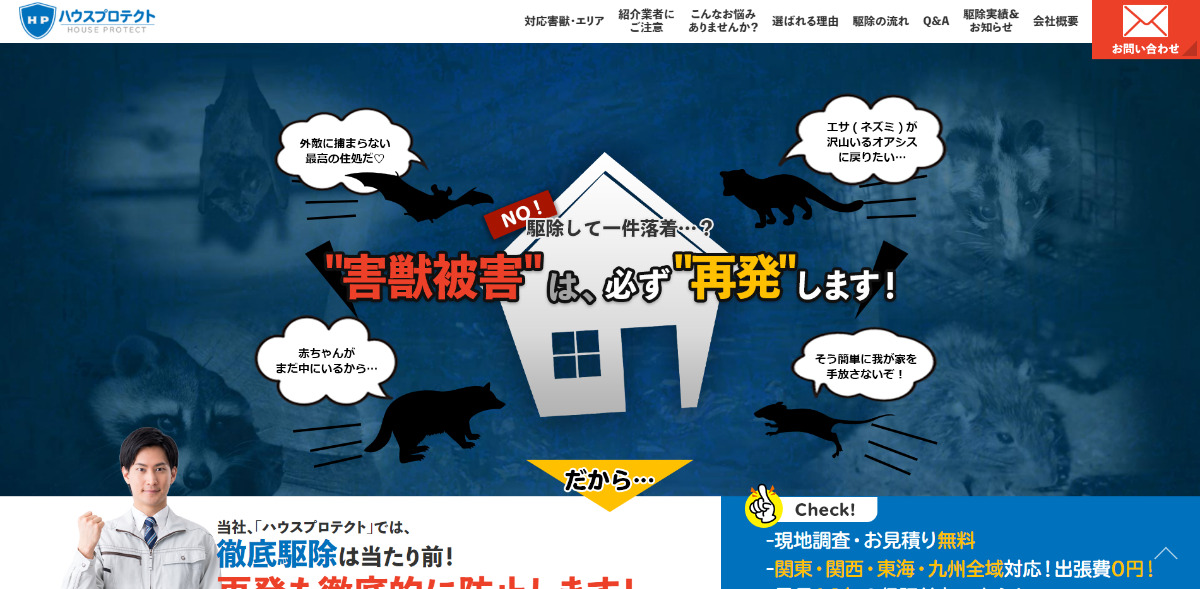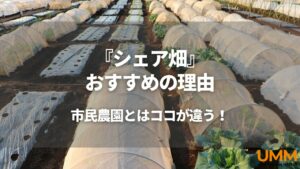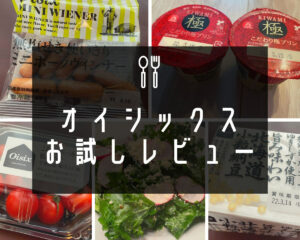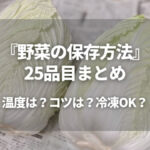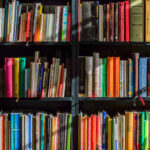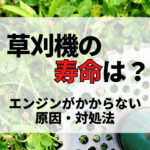【アナグマ】駆除・対策方法まとめ!見つけたら危ないので触らない

※当記事はアフィリエイト広告を含みます。
一般的には馴染みの少ない「アナグマ」ですが、最近では農作物に被害を与えることで注目されています。
害獣としては、イノシシやアライグマ、鹿などが有名です。
しかし、アナグマも上記の害獣と並んで、農作物への被害があります。
対策をしなければ、様々な被害が出るため注意しましょう。
今回の記事では、「アナグマの駆除」を中心に、対策などを解説していきます。
24時間365日対応!
「害獣駆除110番」
目次
アナグマとは

アナグマは見た目が可愛らしいので、害獣に見えないかもしれません。
また、近年、畑だけではなく、一般家庭での被害も増えています。
最初はアナグマの生態と特徴を確認していきましょう。
生態
アナグマは夜行性の動物で、タヌキやハクビシンに似ていますが、イタチ科の動物です。
また、外来種ではなく、もともと日本に住んでいるアナグマで、「ニホンアナグマ」という在来種です。
名前にもなっている通り、穴を掘って巣を作る上に夜行性なので、見かけることは少ないでしょう。
アナグマが住んでいる地域は北海道以外で、広く生息しています。
年中、活動しているわけではなく、冬季には冬眠し、平均温度が10℃を上回ると目覚めます。
春から夏にかけて繁殖し数を増やすため、狩猟期間である冬前から春に駆除すると、被害を抑えられるでしょう。
似ている動物との見分け方
アナグマは全長が50cm、体重は10kgほどが平均的な大きさです。
見た目は、顔がイタチのようにシュッとし、体はタヌキのように丸くなっています。
また、タヌキがアナグマの巣穴に入っていることもあるので、タヌキと間違われることが多いです。
体は白から灰色を基準に、足や目の周り、鼻先は黒くなっています。
性格は温厚なので、人に危害を加えるような話は聞きませんが、農作物への被害は増えています。
【害獣】アナグマによる被害

最近では数が増加し、農作物の被害も拡大しています。
意外ですが、アナグマは一時、絶滅危惧種に指定されていました。
しかし、最近では数が増え、駆除されるケースも珍しくありません。
アナグマによる被害を見ていきましょう。
農作物の被害
アナグマは甘い食べ物が好きなので、いちごやスイカ、トウモロコシなどの被害が多くなっています。
鹿やイノシシほどの被害はありませんが、十分に警戒が必要な害獣です。
基本的には雑食性で、昆虫や木の実といった山や森のものを食べますが、エサが少なくなると人里へ現れます。
また、アナグマは爪が鋭く、地面に穴を掘ることが得意です。
畑の周りに柵などを設置していても、低い箇所から侵入できてしまうため、注意しましょう。
建築物への被害
先ほども解説しましたが、アナグマは穴を堀ります。
主には巣穴を作るためですが、家屋などの近くに穴を掘られた場合には、地盤が緩んでしまうかもしれません。
家屋の床下に住み着くこともあり、床下に大きな穴を掘ることもあります。
地盤が緩んでしまうと、最悪の場合には家屋の倒壊につながります。
また、糞尿の臭いや雑菌など、住み着かれてしまうと様々な被害を与えかねません。
アナグマの対策・撃退・駆除方法

農作物や建物に被害をもたらすアナグマですが、放置するだけではなく、対策は可能です。
ただし、駆除となるとハードルが高いのも事実。駆除を希望する場合はおすすめのアナグマ駆除業者をチェックしてください。
アナグマの嫌いなにおいで予防する
こちらも予防ですが、オオカミの尿でアナグマを近寄らせないようにします。
日本のアナグマには天敵がいませんが、潜在的にオオカミのような肉食獣が苦手です。
オオカミの尿を畑の周りに設置することで、アナグマによる被害を減らせます。
ただし、雨などが続いた場合には効果が薄れてくるため、定期的な交換や雨除けを行いましょう。
また、ミントのにおいもアナグマを近寄らせないようにするために効果的です。忌避剤やおおかみの尿などを使いたくない方は、ミントがおすすめです。
食べ物を畑の近くに放置しない
生ゴミを含む食べ物などを、畑の近くに放置しないようにしましょう。
たとえば、販売できない農作物でも動物から見ると、食べられるものです。
畑の近くまで寄ってきてしまうと、農作物にも被害が及ぶ可能性が高くなりますし、食べ物がある場所と覚えてしまいます。
アナグマを寄せ付けないためにも、畑の周りに廃棄する農作物や、生ゴミなどを放置しないようにしましょう。
アナグマだけでなく、モグラの退治方法やイタチの駆除方法で困っているかたは、放置せずに対処しましょう。
罠を使う【要狩猟免許】
アナグマを駆除するために一番最適な方法は、「罠を使う」ことです。
罠の中でも「箱罠」を使用することが多くなります。
アナグマは中型獣に分類されるため、サイズにあった箱罠を用意します。
基本的には箱罠の中に、アナグマの好物になる農作物や、甘い食べ物を入れて待つだけです。
アナグマの通り道や、農作物の被害があった場所に設置しておくとよいでしょう。
ただし、箱罠の使用には狩猟免許や自治体への許可申請が必要です。
柵で予防する
駆除方法ではありませんが、柵を使って予防ができます。
とくに電気柵が効果的です。
電気柵は、支柱を設置してから電気が流れる電線を設置していきます。
動力はバッテリーや電池、ソーラーなど、様々な方法があります。
どのようなものでもよいのではなく、予防したい動物に対して、適切な電気柵を選びましょう。
アナグマは低い位置を通るので、低い部分にも電線を設置します。
さらに「危険表示板」の設置を忘れてはいけません。
危険表示は周りの人のためでもありますが、法律で定められた義務でもあるため、設置忘れには注意しましょう。
アナグマ駆除の注意点

アナグマの被害が大きい場合には、駆除を考えることになります。
しかし、アナグマは誰にでも捕獲や駆除が許されているわけではありません。
狩猟免許や鳥獣保護法に注意しましょう。
鳥獣保護管理法で守られている
アナグマは鳥獣保護管理法で守られています。
鳥獣保護管理法は、鳥獣の保護と適正化のために制定されています。
アナグマは、タヌキやキツネと同じように鳥獣保護管理法で守られているため、勝手に駆除はできません。
違反した場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
狩猟免許と期間に注意
アナグマの駆除に関しては、「狩猟免許」と「狩猟期間」に注意しましょう。
まず、狩猟免許ですが、アナグマを駆除するために使う箱罠の設置には、狩猟免許が必要です。
狩猟免許の取得には、申請以外に試験を受ける必要があります。
・知識試験
・適正試験
・技能試験
上記、3つの試験を受けなければいけません。
簡単ではないため、勉強は必須です。
また、各都道府県の猟友会が「狩猟免許予備講習会」を開催しているため、受講すると合格の可能性が上がるでしょう。
次に狩猟期間についてですが、基本は北海道と北海道以外で分けられています。
| 北海道 | 10月1日〜翌年1月31日(猟区内:9月15日〜翌年2月末日) |
| 北海道以外 | 11月15日〜翌年2月15日(猟区内:10月15日〜翌年3月15日) |
各地域や鳥獣の種類によっては、上記の限りではありません。
詳しくは、各都道府県の自治体に確認をお願いします。
狩猟期間中であったとしても、地域によってはアナグマの捕獲に許可が必要になるため、罠の設置前には必ず各自治体に確認しましょう。
狩猟免許を持たない場合は予防を
狩猟免許と狩猟期間などについて前述しましたが、狩猟免許は簡単に取得できるものではありません。
まずは、狩猟免許の必要がない予防を考えましょう。
先に紹介した「アナグマの駆除方法」にもありましたが、電気柵などで予防可能です。
捕獲や駆除には狩猟免許は必須ですが、電気柵の設置に免許は必要ありません。
アナグマを含める害獣は、一度、危ない目に遭うと畑に近寄りづらくなります。
ただし、電気柵は人にとっても危険を伴うため、危険表示板の設置や周囲への注意喚起を徹底しましょう。
怪我に注意
アナグマの駆除には箱罠や電気柵を使用しますが、どの方法でも怪我に注意しましょう。
電気柵で周りへの注意喚起はもちろんですが、自分でも設置時や、電源の切り忘れなどで怪我の可能性があります。
また、箱罠も怪我の可能性は十分にあるため、注意が必要です。
とくに子どもが誤って侵入しないように注意しましょう。
罠も予防も、怪我の可能性があるため、自分を含む周りへの注意喚起が必須です。
アナグマの被害だけでなく、イノシシの被害やハクビシンの駆除で悩んでいる方は、早めに対処しましょう。
アナグマのおすすめ駆除業者

ここまでは、自分でアナグマの駆除や予防をする方法を中心に解説してきました。
しかし、アナグマの駆除には狩猟免許が必要であったり、注意すべき点が多くあります。自分でアナグマの駆除を行うのが難しい場合には、専門の駆除業者へ依頼しましょう。
相談・見積もりは無料なので、ぜひ活用してみてください。
おすすめの害獣駆除サービス一覧表
| サービス名 | 対応エリア | 料金 | 見積もり |
|---|---|---|---|
| 害獣駆除110番 | 全国 | 14,300円(税込)~ | 無料 |
| 関東・関西・東海・九州 | 4,500円(税込)〜 | 無料 | |
| 東京・神奈川・千葉・埼玉 | 14,300円(税込)~ | 無料 | |
| 関東・関西・東海・九州 | 要見積もり | 無料 | |
| 全国 | 要見積もり | 無料 |
すぐに依頼したい方におすすめ|害獣駆除110番
| 料金 | 14,300円(税込)~ |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 対応 | 加盟店型 |
| 見積もり | 無料 |
| 公式サイト | 害獣駆除110番 |
特徴:「1匹残らず徹底駆除」がモットー
害獣駆除110番は、愛知県に本社があるシェアリングテクノロジー株式会社が運営する、害獣駆除の紹介サービスです。
24時間受付のコールセンターを設けているので、夜や休日でも相談可能。日本全国に加盟店があり、施工はお住まいの地域の加盟店が担当します。駆除には毒薬を使わない方法を採用し、「追い出し」と「侵入経路封鎖」で行います。
料金目安は、駆除+消毒+清掃の作業を合わせて14,300円(税込)から。無料の現地調査で見積もりを算出し、追加料金は発生しません。
中間マージンなしだから安い|アットレスキュー
| 料金 | 4,500円(税込)〜 |
|---|---|
| 対応エリア | 関東・関西・東海・九州 |
| 保証期間 | 最長5年 |
| 自社対応 | 自社で一貫作業 |
| 見積もり | 無料 |
| 公式サイト |
特徴:全ての作業を自社一貫!
アットレスキューは、2007年に創業して以来、害獣・害虫駆除をメインに経験と実績を積んでいます。
本社は大阪で、全国5箇所に支店・営業所があります。関東地区では、神奈川、埼玉、東京都の一部、千葉県の一部、栃木県の一部。関西地区では大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山県北部。東海地区では愛知、岐阜、静岡、三重。九州地区では福岡が対応可能地域となっています。
代理店を通さず、調査から施工まで全ての業務を自社で一貫しています。中間マージンが不要という強みを活かして駆除費用の「業界最安値」を目指し、基本料金は4,500円(税込)から。他社価格への対抗も応相談とのことです。
相談・現地調査・見積もり提案までは全て無料で、見積もり以上の追加料金はかかりません。また、最大5年間の再発保証がつきます。
首都圏エリア最短20分!|害獣退治屋さん
| 料金 | 11,000円(税込)~ |
|---|---|
| 出張対応エリア | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 |
| 保証期間 | 最長10年 |
| 自社対応 | 自社で一貫作業 |
| 見積もり | 無料 |
| 公式サイト |
特徴:地域密着でスピーディーな対応
![]() 害獣退治屋さんは完全自社施工の害獣駆除業者です。東京、神奈川、千葉、埼玉の4都県に対応し、最短20分で現地調査に来てくれます。
害獣退治屋さんは完全自社施工の害獣駆除業者です。東京、神奈川、千葉、埼玉の4都県に対応し、最短20分で現地調査に来てくれます。
駆除料金の目安は、害獣の種類により変わります。アナグマの料金目安はホームページに記載がありませんが、イタチでは14,300円(税込)から、アライグマでは21,800円からと書かれています。動物の種類がわからなくても応相談です。
相談、現地調査、見積もりまでは完全無料です。ホームページには「駆除の途中で追加必要項目があった場合には都度ご相談」とあるので、不明点は見積もり時によく確認してください。
再発防止も徹底したい方に|ハウスプロテクト
| 対応エリア | 関東・関西・東海・九州 |
|---|---|
| 保証期間 | 最長10年 |
| 対応 | 自社型 |
| 見積もり | 無料 |
| 公式サイト |
特徴:再発防止施工に自信
![]() ハウスプロテクトは、埼玉県に本社がある株式会社GROWTHの害獣・害虫駆除サービスです。
ハウスプロテクトは、埼玉県に本社がある株式会社GROWTHの害獣・害虫駆除サービスです。
対応エリアは広く、関東7都県(東京、神奈川、埼玉、群馬、千葉、栃木、茨城)、中部6県(長野、山梨、愛知、岐阜、三重、静岡)、関西6府県(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)、中四国7県(岡山、広島、山口、鳥取、島根、香川、愛媛)、九州7県(福岡、熊本、長崎、佐賀、大分、宮崎、鹿児島)となっています。
リフォーム会社が母体なので、害獣駆除の知識はもちろん、再発防止施工や被害箇所の原状復帰工事も可能です。万が一の再発に備えて最長10年の安心保証も用意され、再発防止へのこだわりが感じられます。
現場調査・見積もり・出張費用はすべて無料。追加料金は原則として発生しませんが、現場で追加提案をすることがあるそうです。
害虫も一緒に駆除したい時は|ムシプロテック
| 料金 | 要見積もり |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 保証期間 | 害虫種類によって異なる |
| 自社対応 | 加盟店式 |
| 見積もり | 無料 |
| 公式サイト |
特徴:年間実績 1万件
![]() ムシプロテックは加盟店式の害虫・害獣駆除仲介サービスです。年間1万件の出動実績があり、経験豊富な加盟スタッフが専門的な技術や特殊機材を使い、その場所の状況に応じた方法で駆除を行ってくれます。
ムシプロテックは加盟店式の害虫・害獣駆除仲介サービスです。年間1万件の出動実績があり、経験豊富な加盟スタッフが専門的な技術や特殊機材を使い、その場所の状況に応じた方法で駆除を行ってくれます。
ホームページは害虫駆除について中心的に書かれていますが、害獣駆除にも対応しています。料金は要見積もりなので、気になる方は問い合わせてみてください。
その他の害獣駆除業者はこちら
もっといろいろな業者を比較検討したい方のために、より多くのサービスを掲載した記事もご用意しています。害獣のおすすめ駆除業者や料金の相場なども一緒に紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
今回はアナグマの駆除について解説してきました。
最近では数が増え、被害を受ける農家も増えています。
しかし、アナグマは「鳥獣保護管理法」で守られているため、勝手に捕獲や駆除はできません。
狩猟免許を取得するか、鳥獣保護管理法に触れない電気柵などで予防することになります。
また、自分での駆除が難しい場合には、害獣駆除専門の業者を利用しましょう。
アナグマを含む害獣の駆除は大変ですが、対策を行うことで、農作物の被害が減らせます。